ニュー・ホライズンズ無人探査機が冥王星に到達
太陽系の一番端っこで、小さいながらも大きな役目を持つ冥王星は、クライド・トンボー(ローウェル天文台)によって1930年に発見されました。その前に、パーシバル・ローウェルは天王星・海王星の軌道の重力から計算される冥王星の位置を弾き出していたものの、当時の技術と小さい星のため特定には至っていません。
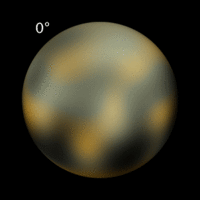
冥王星のシンボルを「♇」と表しますが、占星学・天文学ではパーシバル・ローウェルのPとLを合わせたものとしています。
プルトニウム(Plutonium)の言葉との一致も偶然ではありません。
冥王星が発見された1930年、そして1930年代、核と原子力関連は飛躍的な発展を遂げました。天王星・海王星が発見された時も、それぞれの天体に関連した革新がもたらされました。
占星学的には(占星学は天文学よりも古い)非常に重大な意味を持つ冥王星。名前のイメージどおり、あの世との扉を守る王です。英語ではPlutoで、ローマ神話で冥府の王の名。ギリシャ神話のハデスに対応します。
こちらの世界とあの世を守る扉、オール・オア・ナッシングのキーワードを持ちます。核のプルトニウム的な、人間の手には負えない極度なエネルギーを意味しているのですが、
ニュー・ホライズンズが搭載している電力が、(原子力電池240w)というのも面白いですね。
ケネディ宇宙センター横からニュー・ホライズンズが打ち上げられた2006年当時は、惑星とされていた冥王星。
その後天文学会的には、物理的に小さいからという理由で惑星から外され現在は準惑星となってはいますが、占星学的には非常に大きな意味を持つため除外するわけにはいきません。

探査機打ち上げ後、月には9時間で到達した後、火星・木星・土星・天王星・海王星と、休憩しながらなんとか冥王星の近くまできたニューホライズンズ。
2015年7月14日 11時47分に再接近の予定。ちょうど冥王星がやぎ座に入ったところ。ニューホライズンズは、ミッションが終わったあとはエイリアン(wiki的にはエイリアン)へのメッセージを発する予定だとか。Wikipedia
冥王星の衛星 カロンと占星術的意味
カロンはギリシャ神話では渡し守(三途の川・冥界へと川を渡す役)です。
ニューホライズンズは、カロンの極についても驚く発見をしています!
NASAでは、信じられない予想外のものとして、ポールが暗く映っていると興奮。今後の解明が待たれますが、冥王星は死と再生をも意味する星。
核と命のコントロールは、そう遠くない未来に可能となるかもしれません。
冥王星を取り巻く衛星の動き、未知の生命からの返事や、そしてカイパーベルト(太陽系内外周辺)外への探索が楽しみですね。
2025年 ニューホライズンズの今 太陽系縁外部 カイパーベルトに
ニューホライズンズ(New Horizons)は、NASAが2006年1月に打ち上げた無人宇宙探査機で、主な目的は冥王星とその衛星群、そしてその先にある太陽系外縁天体(特にカイパーベルト天体)の探査です。
この記事を書いた2015年、ニューホライズンズは冥王星に到着し私は興奮したのを覚えています。
それから10年、2025年の今も、ニューホライズンズは旅を続けています。
ニューホライズンズの歴史
-
開発と打ち上げ準備
1990年代後半から計画が始まり、NASAのプログラムの中でも費用対効果が高いミッションとして承認されました。 -
2006年1月19日打ち上げ
フロリダ州のケープカナベラル空軍基地から打ち上げられ、秒速約16.26kmという非常に高速で太陽系の外縁部に向かいました。 -
飛行経路
木星の重力を利用した「スイングバイ」で加速し、打ち上げから約13か月後の2007年に木星をフライバイ通過。 -
冥王星到達(2015年7月14日)
ニューホライズンズは史上初めて冥王星とその最大の衛星カロンを詳細に観測。表面の地形、大気、氷の存在、衛星群の発見など多くの新知見をもたらしました。 -
カイパーベルト天体への探査
2019年1月1日には、冥王星よりさらに遠くにあるカイパーベルト天体「アルティメット・トゥーレ」(正式名称2014 MU69、後に「アロコス」と命名)に接近し、その地形や表面の詳細を観測。 -
通信距離
地球から約70億km以上離れており、通信に往復で数時間かかるため、リアルタイム操作は不可能。 -
科学データの送信
探査データは徐々に地球に送られ、今も解析が続いています。
ニューホライズンズの今後の展望
-
-
さらなるカイパーベルト探査
ニューホライズンズは燃料と機器の状況が許す限り、他のカイパーベルト天体の探査を続ける予定です。 -
太陽系外縁部の研究
太陽系の外縁部、ヘリオポーズ(太陽風が星間物質とぶつかる境界)に近づきつつあるため、太陽系の境界条件の研究にも貢献が期待されています。 -
寿命の限界
燃料や機器の劣化により、2030年代にはミッション終了の可能性もありますが、NASAは状況を見て延命を検討しています。
-
冥王星とカロンに関する主な発見
-
多様で複雑な地形
-
冥王星の表面は氷の平原「スプートニク平原」や巨大な氷の山脈、クレーターの少ない若い地域など、多彩な地形が確認されました。
-
活発な地質活動や氷の移動が示唆され、かつて考えられていたよりも「生きている惑星」のような動きがあることが判明。
-
-
大気の存在と構造
-
薄い窒素とメタンを主成分とする大気があり、高度によって成分の層構造があることがわかりました。
-
大気は日中に太陽光で温められて膨張し、夜間には収縮する動きを繰り返している。
-
-
カロンの巨大峡谷や表面変化
-
冥王星最大の衛星カロンには巨大な峡谷があり、氷の地形の変化も観測された。
-
表面に赤みを帯びた地域があり、これは太陽紫外線が分解した有機物(テラジン)と考えられる。
-
-
衛星群の多様性
-
小さな衛星群(ニクス、ヒドラ、ケルベロス、ステュクス)の表面も観察され、多様な形成過程や衝突の歴史が示唆された。
-
カイパーベルト天体「アルティメット・トゥーレ」(アロコス)での発見
-
形状の予想外の複雑さ
-
当初は単一の球状天体と予想されていたが、実際は細長い形状の連結天体(双子のような形)であることが明らかに。
-
表面には古いクレーターが多く、形成からほとんど変わっていない「太陽系原初の天体」とされる。
-
-
表面の反射率の違い
-
片方の「頭」の部分がもう片方より明るいことがわかり、成分や年代の違いが示唆される。
-
その他の科学的知見
-
太陽系形成の手がかり
冥王星やカイパーベルト天体の詳細な調査は、太陽系誕生時の物質の分布や進化過程を理解する貴重なデータとなっています。 -
太陽風と宇宙環境の調査
宇宙空間におけるプラズマや粒子の観測も続けており、太陽系の外縁部の環境を知る手がかりに。
1. 宇宙探査と人類の意識の拡張
太陽系のひとつの惑星である地球。そこを飛び出した宇宙探査機ニューホライズンズ。
それが太陽系を出る。
世界一、いや太陽系内イチの大きな出来事だと言えます!でもそれを気にする人は多くない。
天王星以降の惑星が発見されたことによって、そのときどきのタイミングで私たちは大変化を経験している。ニューホライズンズが太陽系を出ることは、人類の「限界突破」を示していて、地球の枠組みや既存の物理的境界を超え、未知への挑戦と好奇心が象徴されています。
人間が物理的に体を持ってそこへ到達する必要はない。
土星までしか「見えなかった」昔。天王星は「望遠鏡で見える」ようになると同時にテクノロジーの発展が加速されたのです。
太陽系外のことが詳しくわかってくると、きっと占星術も進化するのでしょう。
そして、ニューホライズンズがもたらした発見により、「まるで生きている惑星」と調査にあるように、冥王星は惑星という冠を奪還できるのでしょうか。
2015年執筆 2025年 追記編集



